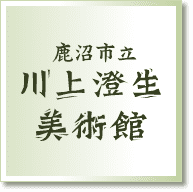長谷川勝三郎
コレクター長谷川勝三郎
鹿沼出身の長谷川勝三郎氏(1912〜2001)は、栃木県立宇都宮中学校
(現 宇都宮高等学校)で川上澄生と出会い、その人柄や版画の魅力に
惹きつけられて、生涯にわたり作品を収集しました。
当館は、その2,000点余の作品提供により開館しました。
ここでは長谷川氏の生涯についてご紹介します。
●川上澄生との出会い
長谷川勝三郎氏は、1912年(明治45)2月9日に鹿沼町大字鹿沼
(現 鹿沼市久保町)に生まれました。
1924年(大正13)、宇都宮中学校(現 栃木県立宇都宮高等学校)に
入学し、そこで川上澄生と出会います。
日光へ遠足に出かけたとき、お宮に自宅の庭園「掬翠園」(きくすいえん)の
千社札を貼っていると、引率していた澄生から声をかけられたのがきっかけでした。
その後、澄生の家へ通って、木版画に惹かれるようになります。
●版画誌『刀』
1928年(昭和3)、宇都宮中学校の版画好きの生徒たちが集まり、版画誌
『刀』(とう)が創刊されます。『刀』は、台紙に小さな版画を貼付け、それを1冊に
まとめたものです。長谷川氏は『刀』創刊の中心となり、実際に澄生の手ほどきを
受けて版画を制作していました。
●新聞社へ入社し、澄生の支えとなる。
長谷川氏は中学校を卒業後、大学進学を経て、新聞社へ入社します。
中学校を卒業したのちも、澄生を慕い続け、神田の画廊に通うなどして
版画作品の収集を始めます。主なコレクションは、川上澄生でしたが、
そのほかにも棟方志功や竹久夢二なども収集していました。
1972年(昭和45)に澄生は亡くなりますが、2人は50年にも及び
交流を続けたのでした。
●川上澄生美術館の開館
1992年(平成4)、長谷川氏は貴重なコレクション2,000点余を郷里である鹿沼へ
提供することを決断し、川上澄生美術館は開館しました。
美術館開館ののちは、名誉館長として恩師川上澄生の魅力を伝えるべく尽力
しました。
長谷川氏は2001年(平成13)、89歳で亡くなりました。